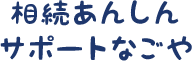相続財産の評価~容積率~

相続税の申告で評価の金額が変わってくるものは土地の評価です。
そして、土地の評価を左右するものの一つに容積率があります
目次
税理士試験では都市計画法や建築基準法は習いませんので、容積率を検討しない税理士が実は多いのではないかと思います。
容積率とはいったい何なんでしょうか?お家を建築された方はご存知でしょうが、容積率とは建築するうえで大事な指標です。
2つ以上の用途地域にまたがっている土地なのかをまずは判断する
相続税評価は基本的に正面の路線価に対して評価対象の土地の面積をかけて評価を計算します。
しかし、その路線価は接道している土地の評価の為の路線価ですので、2つ以上の用途地域にまたがっていた場合は、単純に面積をかけただけでは、高い評価になる可能性が高くなります。
そのためには、容積率が違う地域にまたがっているのかを判断します。
最近ではそれぞれの市区町村にてHPが整備されネットで確認することができます。
名古屋市在住の方はこちらでご自身の対象のお土地を検索してみてください。
いかがでしょうか?こちらで用途地域を確認した後は、容積率を確認してください。
それでは容積率とは何でしょうか?
容積率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合のことを言います。例えば、100㎡の土地に容積率200%の土地であれば、200㎡までの延べ床面積の建物が建ち、400%の土地であれば、400㎡までの延べ床面積の建物が建てられるということです。200%の場所で2階建てが建てられているのであれば、単純に400%の場所では4階建てが建てられるということです。
パーセンテージが少ない地域より、大きい地域の方が空間をより有効に活用できるので、通常土地は高く取引されることになります。
30坪程度の戸建ての土地であればあまり、複数の用途地域にまたがっていることは少ないのでしょうが、マンションなどの大規模な土地になると2つ以上の容積率にまたがっている可能性が高くなっているのでご注意ください。
前の記事 : 相続セミナー(事例でわかる!相続対策の勘どころ)
次の記事 : 名古屋市の建物の解体で最大40万円の助成金?!