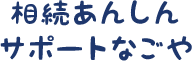2023/08/01
インターネットの節税スキームはご注意を

目次
先日、30代ぐらいの女性の方から、アパート経営をしたいというお問い合わせがありました。
「昨今は、一時期のサラリーマン大家さんの影響から利回りが非常に悪く、いい物件は少なく厳しいですよ」とご説明しました。
話を聞くと、3000万円の収入がある夫が、不動産所得から損失がでても、損益通算して還付が望めるからと1億円程度で中古のアパートはないかと
いくつかのアパートをご紹介させていただきました。
なるべく、資産性や入居率が高く、築浅で、大規模修繕時に損失が出た場合に損益通算できますよとシミュレーションを作りご提案をさせていただきました。
イメージは「15年程度で初期費用をすべて支払い、15年以降、残りはすべて収入になり年金になります、資産性の高い不動産は最後に残ります。」というご提案をしました。
ところが、
「いや違います、耐用年数が過ぎたアパートを買い、大きく減価償却費をだすことにより損失を出して損益通算をしたいんです、税率が40%なので損失を出せればその分、還付できるんです。」というものでした。
<ご希望のスキームのまとめ>
木造アパートの耐用年数は22年です。耐用年数が過ぎていれば4年で、購入金額を減価償却できるので、大きく損失を出して、給与の収入と相殺できるというものです。
例えば、4000万円で購入したら、年1000万円を経費として4年にわたり減価償却で損失にでき、収入が3000万円であれば、その損失と相殺でき、前払いで払っていた税金40%の税率分を還付できる。
さらに購入5年後に売却することにより、譲渡所得税は15%で売り抜けることができる。その税率40%と15%の格差を利用する節税スキームでアパートを買う。というものでした。
とんでもなくピンポイントなスキームで一瞬ギョッとしましたが、このスキームおかしいのです。
①耐用年数が過ぎた木造アパートの建物にどれだけ減価償却できるのか?
購入金額から土地と建物を区分して建物部分のみ減価償却をします。購入した土地からは減価償却できません。
通常、固定資産税の評価額などから、土地と建物をわける。あるいは売主の簿価などから、売買契約書に土地と建物を分けて記載した金額で区分
いずれにせよ、5000万円のアパートだとしても、5000万円を減価償却できるのではなく、減価償却が終了した木造アパート部分しか減価償却することはできません。
そして、耐用年数の過ぎた建物に大きな金額の簿価はつきません。
試しに事業計画表を作成してみました。
小牧市 5380万円 全5戸 満室 木造 2000年築 (実際のアパート)
5380万円のうち建物は736万円で4年で償却できるものの、年184万円しか減価償却できません。
購入1年目にはその他購入時に係る諸費用などを経費に入れると、かろうじて赤字にすることができましたが、2年目から4年目はほぼトントンながら黒字になりました。
黒字だということは、5棟あろうが10棟あろうが、赤字にはできないという計算です。
もし、おおきな赤字だということであれば、そもそも収益性が低く、銀行の借り入れもできないダメな物件ということができます。
あまりにもピンポイントなスキームでネットでもみたのではと思い、ご相談者様の数字やキーワードからyoutubeで検索すると一件ズバリがヒット
youtubeのチャンネルを実際見ると、いかにもという説明の仕方で、大事なところは説明していなかった印象があります。
インターネットは検索するとすぐにでて便利ですが、それを信じてしまうのは要注意です。
前の記事 : 移民から考える 究極の負け組土地、勝ち組土地
次の記事 : 相続税の税制改正のセミナー 2023年8月3日