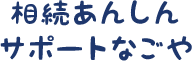相続財産の「使い込み」が急増中——見過ごされがちなリスクとその対策

親の死後、兄弟姉妹の関係が一変した——そんな話は決して珍しくありません。
特に近年、相続人の一人が他の相続人に無断で財産を使い込む「使い込みトラブル」が急増しています。
2025年5月に公表された家庭裁判所の統計によると、相続財産の管理や分割を巡って家庭裁判所に持ち込まれる「審判」の申し立て件数は年々増加傾向にあります。
背景には、遺産分割協議が完了していない状態で、相続人の一人が勝手に銀行預金を引き出したり、不動産を売却してその代金を自己のために使ったりするといった行為があります。
■なぜ「使い込み」が起きるのか?
使い込みが起きる主な理由は、以下の3点に集約されます。
遺産分割協議の遅延・放置
相続発生後、相続人同士の関係性や連絡状況により、協議が円滑に進まず、放置されるケースが多くあります。財産管理権限の誤解
例えば、被相続人の預金口座に代理人登録されていた相続人が「自分にもらう権利がある」と誤解し、引き出してしまうケースがあります。金銭感覚のズレ・経済的事情
経済的に困窮している相続人が、生活費や借金返済のために安易に手をつけてしまうこともあります。
■家庭裁判所に頼る前にすべきこと
家庭裁判所に申し立てるのは最終手段です。コストも時間もかかります。まずは以下のステップで予防と対応を図ることが望ましいです。
相続開始後すぐに遺産の凍結を行う
金融機関に連絡し、被相続人名義の口座を凍結しましょう。不動産は名義変更が済むまで売却ができませんが、念のため登記簿の確認もしておくべきです。相続人間で早期に協議開始する
感情的な問題に発展しないうちに、できる限り専門家を交えて協議を進めることで、トラブルの予防につながります。使い込みの証拠は冷静に集める
もし不正な引き出し等があった場合は、通帳の写しや預金の動きを示す証拠を集め、事実関係を整理しましょう。
■専門家の立場からの提言
相続問題の多くは、「人の感情」と「お金」が密接に結びついているため、法的な解決だけでは根本的な解決に至らないこともあります。
相続税対策ばかりに意識が向きがちですが、実は“相続の実務”や“人間関係の整理”こそが重要です。
私たち税理士や司法書士、弁護士といった専門家は、単なる申告の代理人ではなく、「家族の再構築の支援者」でもあります。相続が「争族」にならないためには、生前の準備(家族信託・遺言・財産の見える化)と、相続後の冷静な対応が不可欠です。
■まとめ
相続財産の使い込みは、予期せぬ家族間の対立を引き起こす深刻な問題です。
しかし、対策を講じておけば未然に防げるケースも多く存在します。
トラブルが顕在化する前に、「誰が、どの財産を、どのように分けるか」を明確にする努力を惜しまず、必要に応じて専門家を早めに介入させることが、平穏な相続への第一歩です。
前の記事 : 相続された資産が狙われる時代──証券口座乗っ取りのリスクと対策
次の記事 : 【相続登記義務化1年】それでも残る空き家問題と新制度への期待