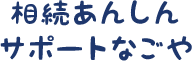【相続登記義務化1年】それでも残る空き家問題と新制度への期待

2024年4月、相続登記の義務化制度が正式にスタートしてから、まもなく1年が経ちます。この制度は、相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記申請をしなければならないというものです。違反すれば、10万円以下の過料が科される可能性があり、相続人の権利と責任を明確にすることを目的としています。
しかしながら、制度開始から1年が経過しても、依然として登記未了の不動産が多数存在し、空き家問題は深刻化したままです。
目次
■相続登記が進まない背景とは?
なぜ制度が始まっても、相続登記が進まないのでしょうか。背景には以下のような要因があります。
相続人同士の関係が希薄化している
兄弟姉妹が全国に散らばり、連絡を取ることすら困難というケースが増加。協議が難航し、登記が先延ばしになることも。費用・手間の心理的ハードル
登記には登録免許税や司法書士報酬が発生します。手続きの煩雑さもあって、特に資産価値が低い不動産では放置されがちです。相続人の“登記の必要性”への理解不足
相続登記は「義務」になったとはいえ、認知度がまだまだ浸透していない現実があります。
■空き家対策としての“新制度”とは
このような状況を受けて、総務省は新たに「簡易な登記支援制度」の導入を検討中です。これは、相続人の所在が不明な場合や、登記が長年放置されている不動産について、地方自治体が中心となって手続き支援を行う制度です。
また、簡素化された調査手続きや、登記申請の代理支援を行うことで、相続人の負担を軽減し、よりスムーズな登記移行を図ることが目的とされています。
■税理士の視点:相続は「生前準備」で差がつく
私たち税理士の立場から見ると、空き家や未登記不動産が残る原因の多くは、生前の準備不足にあります。
遺言書の未整備や、不動産の分け方の合意形成を怠ることで、結果として放置された不動産が増えてしまいます。
また、評価額が低くても、固定資産税は発生し続けます。
さらには草木の放置、老朽化による近隣トラブルといった社会的コストも看過できません。
今後の相続においては、「節税対策」だけでなく、「管理できる財産にする工夫」がますます重要になってくるでしょう。
■まとめ:登記義務化を“空き家解消”につなげるために
登記義務化は一歩前進ですが、それだけでは解決に至りません。今回のような新制度の導入を機に、「相続=手続き」だけではなく、「相続=地域資産の再生」と捉える視点が求められます。
空き家を未来の負債にしないために、早期の相談と対策、そして生前の準備がカギを握ります。
登記や財産整理に不安がある方は、専門家への相談を早めに行うことを強くおすすめします。
前の記事 : 相続財産の「使い込み」が急増中——見過ごされがちなリスクとその対策
次の記事 : 中古マンション価格は“全国的高騰”へ——名古屋圏も例外ではない?