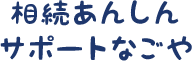土地の相続税の評価方法を知ろう!

相続財産の多くを占めるのは預金や現金でなく、不動産である方が多いと思います。
目次
それであれば不動産の財産評価が、相続財産の内どのくらい占めるかを把握しなければいけません。
把握することにより、はたして相続税は発生するのか?相続税はいくらかかるのか?遺留分はいくら現金で用意しなければいけないか?相続財産のうちの現金で遺留分は間に合うのか?兄弟で分けることができるのか?
様々な問題の整理をすることができます。
不動産の相続財産の計算方法として大きく2つの方法があります。
それは路線価方式と倍率方式になります。
国税庁が出している路線価図・評価倍率表をご確認ください
路線価方式・・・
路線価方式では主に住宅街に指定がされています。例えば、上記、路線価図を見ていただくと前面の道路に金額が記されています。例えば、「70E」と表記があれば、(Eは借地権割合なのでいったんおいておきます。)70という数字に1,000をかけた70,000が1㎡の価格になりですので、それに面積をかけた数字が相続税の評価金額となります。面積が100㎡であれば、7,000,000円であるとなります。
但し、正確には不整形地や造成が必要であれば評価減を7,000,000円からすることになります。つまり7,000,000円はMAXの金額を割り出したということになります。
一度、路線価を調べて、面積をかけてみてください。大体のざっくりした金額を把握することができると思います。
路線価でない簡易方法・・・
相続税の評価方法ではありませんが簡易に計算する方法として、固定資産税の評価額に1.14をかけるという方法があります。
固定資産税の評価額は実勢価格(相場)の7割、路線価は実勢価格(相場)の8割で作成しているというものから、固定資産税から相続税の評価額を簡易的に出すものです。
例えば実勢価格100万円の土地の評価は固定資産税の評価額は70万円(7割)として評価されているものとされていますし、路線価は80万円(8割)と表記されています。
であるならば70万円に1.14をかけると79.8万円となりおよその路線価が出るということですね。
倍率法・・・
倍率法は市街地でないところに設定されていまして、固定資産税の評価額に倍率をかけることにより、相続税の評価額を出すやり方です。現況を確認し、田であれば、そして農業振興地域(青地)か否かを確認し、表からみて何倍をかければいいのか読み解きます。例えば固定資産税の評価額が50,000円で40倍のエリアであれば、2,000,000という具合です。
倍率法は固定資産税の評価額から乖離する場合がありますので、そのまま固定資産税の評価額で考えていると間違えてしまうケースがあります。
また、現況が駐車場などの雑種地などの場合、住宅地として評価すればいいのか?田畑に準じて評価すればいいのか非常に難しい判断になります。固定資産税の評価額が安くても住宅地として評価しなければいけない場合は思った以上に価格が高くなるケースがあります。
初めは、そこまで精度の高いものは不必要ですが、ざっくりとした全体像を把握しておくことが必要になるかと思います。
また、兄弟で分ける場合にいくらくらいのものであるかわからない事には、相続税の評価額をある程度分かっていえば分割案も作成しやすいと思います。
前の記事 : ある時、急に相続人になったら・・・
次の記事 : 建物の相続税の評価方法を知ろう!