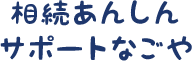2022/08/08
不動産鑑定評価と相続税評価の関連性

相続税評価は時価であると定義がされています。
「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引がおこなわれる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」
時価と言われてもいったい何のことなのが、わかりかねます。そのため、
相続税評価の時価とは国税庁の「財産評価基本通達」に基づき計算したものを時価と判定しています。
時価≒財産評価基本通達ということにしています。
財産評価基本通達が時価として原則、採用をすべき金額となりますが、
メリット:公平な租税負担ができる
デメリット:個別性の反映が十分でないケースがある。
相続税の申告は納税者自身がしなければいけません。画一的な計算方法により、計算しやすくもなります。
問題は、時価と財産評価基本通達と乖離している場合です。
財産評価基本通達は画一的な計算方法なので、それが実際の取引価格=時価ではないのは明らかです。
そこで、納税者としては、これこれこういった事情により、財産評価基本通達ではとても実態を表した評価になっていないとその場合には不動産鑑定評価の金額を採用しようという判断になります。
そして、税務署サイドとしてはそんなことをいちいち採用できるのであれば、税務署側としては、課税の公平性の担保できない。財産評価基本通達に従い計算してほしいというのが本音です。
や税務署の手続きが煩雑になるので、認めたくないところでしょう。
財産評価基本通達の定めによらない財産の評価について-裁判例における「特別の事情」の検討を中心に-
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」とあります。
財産評価基本通達により算出した金額が」気に入らないからと言って不動産鑑定士に鑑定評価書の作成を依頼すれば、認められるものではなりませんし、節税になるものではありません。
前の記事 : 30年を迎え、宅地にできる生産緑地はそれほど多くない
次の記事 : 「路線価に基づく相続財産の評価は不適切である」という最高裁判決 令和4年4月19日